2025年お米の価格上昇が止まらない中、全国農業協同組合中央会(JA全中)会長の山野徹さんが「コメ価格は高くない」と発言し、農業界や消費者の間で大きな話題となりました。
この発言の背景にはどのような農業政策の意図があるのでしょうか。
山野徹さんの発言を踏まえ、コメ価格に対する考え方と、山野さんが見据える農業政策の行方を深掘りしていきます。
山野徹(JA会長)の「コメ価格は高くない」発言の理由はなぜ?
価格が上昇している中、山野徹さんが発言した「コメ価格は高くない」という言葉は、消費者と農家に異なる反響を引き起こしました。
山野徹さんが伝えたかった本当の意図について考察します。
山野徹さんが「コメ価格は高くない」と発言した背景には、農業経営の厳しさや生産者の収益確保の必要性があります。
近年、農業資材や燃料費の高騰により生産コストが増加しています。
農家が受け取る「生産者米価」は過去と比べて抑えられている傾向にあり、生産コストを考慮すれば適正価格よりも低い場合もあるそうです。
山野徹さんが「高くない」と明言したのは、コメ価格が適正であることを訴えることで生産者の収益を守り、持続可能な農業を実現しようという意図があると考えられます。
こうした生産現場の苦境を広く理解してもらいたいという強い想いからでしょう。
消費者にとってはコメ価格が高いと感じますよね。
しかし農家の立場から見ると、現在の価格では生産が赤字に近いケースも多く「高くない」という認識になるのではないでしょうか。
生産コストの増加や農業経営の厳しさを考慮すると、現在のコメ価格は生産者にとって適正であり持続可能な農業を維持するためには必要な水準なのかもしれません。
消費者と生産者の双方が納得できる価格設定を目指すことが、持続可能な農業の実現につながると感じます。
山野徹さんの経歴はこちら↓↓
山野徹(JA会長)の農業政策の意図とは
山野徹さんの意図は、単純な価格の引き上げではなく、農業そのものが持続できる環境をどう作るかにあるのではないでしょうか。
米農家にとっては、資材価格の上昇や人口減による販売量の低下などが重なり、厳しい経営が続いているからです。
山野徹さんが繰り返し強調しているのは「農家が適正な利益を得られる価格水準の確保」です。
これは単なる営利追求ではなく、次世代への農業継承や地域の雇用創出、そして農村の維持に不可欠な要素です。
また、山野徹さんの政策意図には「地域主導の農業モデルの推進」もあります。
JA全中主導の農業政策では限界があるとの認識から、JAや地方自治体が一体となり地域に適した作物や販売ルート、加工・販売までを自立的に構築できる体制を目指しているそうです。
これは単なる価格の議論を超えた「農業の構造改革」にもつながる重要な視点ですよね。
山野徹さんは、米価を適正に保つことが、安全保障・国民生活・地域の未来を守る政策だと位置づけています。
山野さんの発言や方針からは農家の現場に寄り添う姿勢と将来を見据えた広い視野が伝わってきます。
価格だけに注目せず、「なぜこの政策が必要か」を考える大切さを改めて感じました。

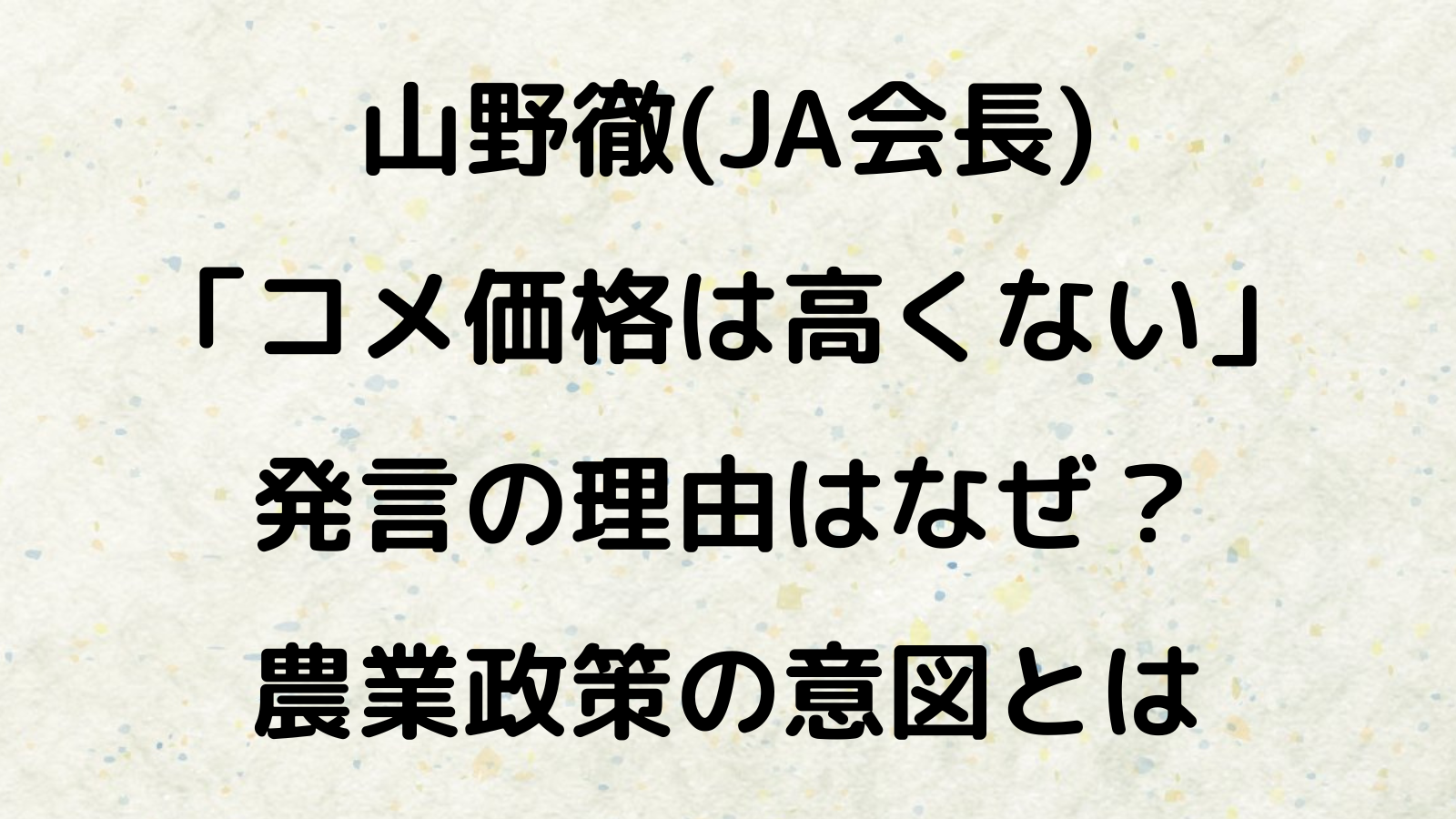

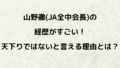
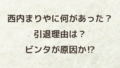
コメント